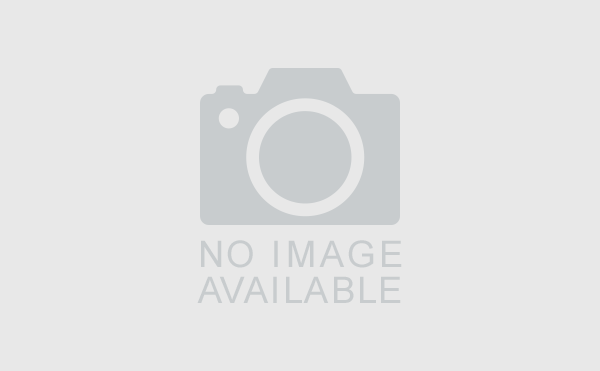睡眠薬って怖くない?
皆様こんにちは、横浜呼吸クリニック副院長の小野容岳です。
眠れない夜が続くと、本当に辛いですよね。楽しい日も大変な日も、最後は睡眠という時間を迎えますし、夜が明ければまた次の日があるわけですから。
実際に当院にいらっしゃる患者さんのお話をお聞きすると、眠れないことや、それによって翌日の体調がすぐれないことなど、様々なお困りごとがあります。
そんな「不眠」という症状を解決する上で、睡眠薬はとても重要なポジションにあります。
ただ、その過程で「薬に頼って大丈夫かな?」と心配になるのも自然なことです。ちょっと怖いような気持ちがあってもおかしくありません。ただ、結論から言うと、専門家の指導のもとで使う限り、睡眠薬は安全に使えます。そして治療は「薬だけ」ではありません。眠りを妨げている原因を一緒に見つけて整えること、さらに最終的には薬を卒業することがゴールです。ここでは、その道筋をわかりやすくお伝えします。
1) 「専門家の指導下なら安全」は本当?
はい、本当です。一言で睡眠薬と言っても、寝入りを助けるお薬、途中で起きないようにするお薬、依存性が低いお薬、お口の中で溶けてくれるお薬、時差ボケの調整に適したお薬など、様々な効能、効果があります。そして、種類だけでなく、一回で飲む量も患者さん個人に合わせて調整するんですね。日本睡眠学会や米国睡眠医学会においても、たびたび「眠れない」といった症状がある方に対して、オレキシン受容体拮抗薬、非ベンゾジアゼピン、メラトニン受容体作動薬などの適切な使用を推奨しています。ちなみに、適正量であるかぎり、寝酒で眠るよりも確実に人体にとっては安全です。アルコールは脳全体が麻痺するので眠れますが、100%睡眠の質を下げます。晩酌で適量召し上がる分には良いのですが、ガツんと寝酒をあおる・・・というのはやめた方が良いでしょう。特にご高齢の方は、転倒・せん妄などのリスクが上がるため、薬の種類や量をより慎重に選びます。ここも医師と二人三脚で調整が必要ですね。
2) 「薬だけに頼らない」—妨げている因子を一緒に探す
不眠には“背景”があります。薬で一時的に眠れても、背景がそのままだと再発しやすいのです。そこで、治療と並行して原因探しをします。
例えば・・・
- 生活リズム:就寝・起床時刻のばらつき、長い昼寝、夜勤・交代制
- 環境・刺激:寝る前のスマートフォン・PC操作、照度の高い照明、カフェイン(コーヒー・エナジードリンク)、アルコール、喫煙
- からだの要因:痛み・かゆみ、頻尿、喘息、鼻づまり、胃食道逆流、甲状腺疾患 など
- こころの要因:不安・落ち込み、ストレス、「眠らなきゃ」の焦り(これが意外に強敵です)
- 睡眠を妨げる病気:むずむず脚症候群、概日リズム睡眠障害、睡眠時無呼吸症候群(いびき・無呼吸) など
近年認知行動療法(CBT-I)という、睡眠の環境整備だけでなく、睡眠の認識、実際の睡眠前後の行動などを整理していく治療法に注目が集まっており、非薬物療法(お薬を使わない治療法)としての研究や実証が進んでいます。ひとまず自宅でできることとして、「今日は眠れたな」という日や、「なんだか眠れなかったなぁ」という日があると思います。それらを記録し、日中の行動、召し上がったもの、楽しかったこと、嫌だったことを振り返ってみましょう。そうすると、眠れた日と眠れなかった日との間に、何か違いがあるのではないでしょうか。ここでよく、「理想の睡眠ってなんでしょうね」というご質問をいただきます。私の私見ですが、小学生の頃、運動会やプールの授業でたくさん体を動かし、夜になって家でお風呂に入り、カレーを食べたらもうウトウト・・・という1日が理想なのではないかなと感じています。つまり、朝のうちに起床し、よく紫外線を浴びながら体を動かし、入浴して体を休め、夕食をいただくという一連の流れは実に健康的であると思うのです。もちろんお仕事をされている場合、こんなスケジュールで過ごすのはなかなかハードルが高いですが、100%の正解を求める必要はありません。今よりも、もう少し体に優しい、眠りやすい行動を心がけるのです。できれば、無理しない範囲で、毎日続けられる方法で。当院は必要な患者さんには勿論お薬を処方しますが、一方でお薬以外のアプローチが必要な方には、その気付きを促すアプローチも実践します。
3) 目標は「薬の卒業」。最初から“出口設計”を
睡眠薬はゴールではなく、回復までの橋渡しです。多くの睡眠に関するガイドラインも、症状が落ち着いてきたら、医師の指導のもと減薬・中止を計画的に試みることを勧めています。また、睡眠時無呼吸症候群やむずむず脚症候群、うつ病など、「眠れない」という症状がありつつも、別の治療法を要する病気はたくさんありますので、そういった病気の可能性を調べることも大事です。
いずれにせよ、眠れないという症状はとても辛いので、まず緊急避難として適正量の睡眠薬に助けてもらうのは、良いプランです。そして、一旦眠れるようになり、ご自身の生活、スケジュールなどを振り返る余裕ができたら、主治医と相談しながらお薬を弱められないか、お薬の飲む頻度を減らせないか、トライしてみるのです。ここで注意ですが、急にお薬を全て中止!といった対応をしてしまうと、一気に症状が悪くなることもあるので、あくまで処方している医師に相談した上で慎重に進めましょう。勿論トライした上でお薬をやめるのが難しいケースもあると思います。その場合は、最小量にできるか、あるいは依存性等が少ない種類のお薬に変えられるかなど、できる範囲での調整が大事ですね。
4) よくある質問
Q. どれくらいの期間、飲んだ方がいいんですか?
A. 個人差があり一概にお答えできませんが、生活習慣や嗜好品などを整理し、眠れない原因が明らかになると、卒業しやすくなります。
Q. お酒と一緒に飲んでもいい?
A. だめです。予期せぬ強い眠気・呼吸抑制・転倒リスクが上がります。事故や健康被害の原因となりますので、避けてください。
Q. 朝に眠気が残るのが心配…
A. 薬の種類や量、飲むタイミングを調整できます。お薬によって、効果が短いものから長いものまであります。ただし、運転や危険作業がある方は必ず申告してください。
Q. サプリで代用できますか?
A. 期待ほどの効果がないことも多いようです。相互作用の心配もあるので、主治医に相談されることをお勧めします。
※本コラムは非医療従事者向けの解説です。患者さんの病態や症状などによって最適解は変わりますので、治療について自己判断せず、必ず主治医と相談してください。