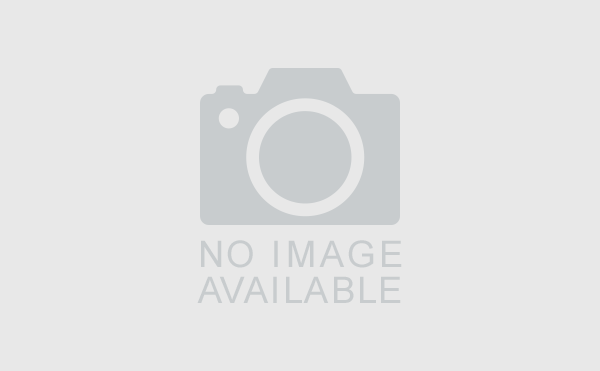はじめての「閉塞性睡眠時無呼吸症候群」受診ガイド
皆様こんにちは。副院長の小野容岳です。当院は閉塞性睡眠時無呼吸症候群、いわゆる”無呼吸”の診断、治療を開院当初より実施しております。この“無呼吸”ですが、じわじわと認知が広がっている一方で、どのような検査を行うのか分からず不安に思っている方が多いようです。今回は、睡眠専門医療機関への受診を検討されている方に向けて、当院の受診や検査の流れに関して解説してみたいと思います。
はじめに
「いびきが大きい」「夜中に何度も目が覚める」「日中の眠気で仕事に集中できない」「家族から呼吸が止まっていると言われた」などなど、睡眠にまつわるお悩みが続いている場合、「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)」の可能性が考えられます。このOSAを放っておくと交通事故や労働災害のリスクになりますし、高血圧、糖尿病、不整脈、脳卒中、心筋梗塞、認知症など様々な病気を悪化させることがあります。ここ数年間で発表された論文でいえば、新型コロナウイルス感染症の重症化因子として、未治療のOSAが大きな悪影響を及ぼしていたことも知られています。実際にクリニックへいらした際は、段階的に負担の少ない検査から始め、必要に応じて精密な一泊検査につなげていくのが基本です。ここでは「初診」「簡易検査(在宅)」「ポリソムノグラフィ検査(精密)」の流れをわかりやすくご紹介します。
1. 初診の流れ:お困りごとをお聞きし、全体像をつかみます
① 問診(症状の整理)
まずは現在のお困りごとを詳しくお聞きします。いびきの程度、夜間のトイレ回数、起床時の頭重感や口の渇き、昼間の眠気、居眠りの有無、ご家族の目撃情報など、睡眠だけでなく、日常生活についてお聞きします。お薬や生活習慣、持病(高血圧・糖尿病・不整脈・心不全など)も確認します。これらは治療方針を決めるうえで大切な材料なのです。睡眠を妨げる病気はとてもたくさんあり、実は甲状腺の病気やうつ病など、気管支喘息など、全く別の病気が原因で睡眠の質が下がっていることもあります。当院ではX線検査や呼吸機能検査、血液検査なども実施可能ですので、必要な検査が何かを考えつつ、病気のストーリーを明らかにしていきます。
② からだの確認(診察)
身体診察では、主に鼻づまりの有無、口の中やのどの広さ、あごや首まわりの特徴、血圧・体重などを診ます。OSAは「のどの通り道が狭くなること」や「ベロの根元が落ち込んでくること」が根底にあり、体格や顔面・口腔の形も大きく影響するためです。実は我々アジア人は、肥満でないOSAの方が欧米人に比して多いと言われております。そのため、肥満がなくても睡眠に関してお困りごとがあれば、十分OSAを疑うキッカケになります。
③ 受診後の見通し(検査の計画)
症状や診察結果からOSAが疑われる場合、まずご自宅で実施できる「簡易検査」をご提案します。その中で、足の異常な感覚がある方や、悪夢の中で手足を動かしてしまう方、より正確な重症度判定が必要な方に対して一泊二日の精密検査(ポリソムノグラフィ)をご提案します。なお、どちらも保険診療の範囲でお受けいただけます。
2. まずは自宅で「簡易検査」を
どんな検査?
鼻と指先に小さなセンサーをつけて、一晩の呼吸の状態、酸素の下がり方、脈拍数などを記録します。入院は不要ですので、ご自宅で普段に近い眠りの中で測定できるのが利点です。機器はクリニックでお渡しし、翌日に返却していただきます。お渡しする際は使用方法についてスタッフが丁寧にご説明しますので、少し時間に余裕をもって来院していただく必要があります。返却は物品の確認のみですので、数分で完了します。また、指のセンサーを使用する関係で、マニュキアは取っていただく必要があります。
わかることと検査の限界
この検査機器では、眠っている間に「息が止まる・浅くなる」回数の目安や、酸素の下がり方がつかめます。OSAの可能性が高いかどうかを見分ける(スクリーニング)のに適しており、重症の判定を得た場合は、そのまま治療へ進むための根拠になります。なお、保険診療のルール上、この時点でAHI 40/h相当(睡眠中、平均して1時間あたり40回以上呼吸が弱くなったり止まっている状態)であったと判定された場合、CPAPと言われる治療機器の処方が可能になります。一方で、眠りの深さや脳波など睡眠そのものの質はわからないため、結果がはっきりしなかったり、重症度と実際の症状がかけ離れていたり、別の睡眠の問題が疑われるといった時は、精密検査が必要になります。
3. より正確に調べる「ポリソムノグラフィ検査」
どんな検査?
一晩かけて、脳の働き(脳波)・呼吸・胸やお腹の動き・酸素の下がり・心電図・いびき・体の動き・目の動き・あごや脚の筋肉などを同時に記録します。具体的には、頭や顔に20チャンネル以上の電極を貼り付け、また指や胸、お腹、足にセンサーを付けた状態で眠っていただきます。眠りの深さやリズムまで把握できるため、OSAの診断・重症度の判定に加えて、他の睡眠の問題の有無も確認できます。これが最も詳細な検査方法です。多くは一泊入院で行いますが、条件が整えば在宅で実施できる場合もあります。当院では最も正確に測定を行えるよう、患者さんがお休みになっている間、睡眠専門医と睡眠専門検査技師が脳波をリアルタイムで確認し、判定しています。
結果の見方
精密検査では、「1時間あたりに、息が止まる・浅くなる回数の平均値」を示しています。数値の目安として
- 5以下:正常
- 5〜15回:軽症
- 15〜30回:中等症
- 30回以上:重症
と分類します。症状(眠気の強さ、生活やお仕事への影響など)も合わせて総合的に判断します。この数値と症状の強さを踏まえ、治療について患者さんの生活スタイルやニーズに応じて相談していきます。
4. 検査の後は・・・
検査を実施したら、そのあとの治療へ結びつけることが大切ですよね。睡眠の課題はOSAだけでないことも多いので、生活の整え方も土台として大切です。体重管理、鼻の通りをよくする工夫、飲酒・就寝前の食事・寝る体勢の見直しなど、できることを一緒に考えましょう。運転や危険作業のリスクについても、その方の状態に応じて具体的に助言します。職場の求めに応じ、就労上の注意点などを記載した診断書をお書きすることもできます。
機器を使う治療が必要なとき
中等症や重症のOSA(簡易検査上AHI40以上、あるいは精密検査上 AHI20以上)で眠気などの症状が強い場合には、マスクを通じてやわらかな空気を送り、のどの通り道がつぶれないようにする治療(CPAP療法)を実施します。軽症の方は、歯科の先生にご協力いただき、下あごを前に出すマウスピースの作成を検討します。なお、心臓のご病気や糖尿病、緑内障などのご病気をお持ちの方は、とくに早めの検査をお勧めします。OSAはこれらの疾患と密接に関係していますが、OSA治療で病気の進行や死亡リスクを下げられるということも報告されており、健康寿命を伸ばすためにも早期診断、早期治療が重要です。
参考資料
- 日本呼吸器学会「I-05 睡眠時無呼吸症候群(SAS)」
- 日本睡眠学会関連誌『睡眠医療ネクサス』
- 日本呼吸器学会『睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン2020』
※本記事は、最新の学会資料・ガイドラインに基づいて作成していますが、検査や治療の進め方はお一人おひとりの状況で異なります。受診時は担当医とご相談ください。