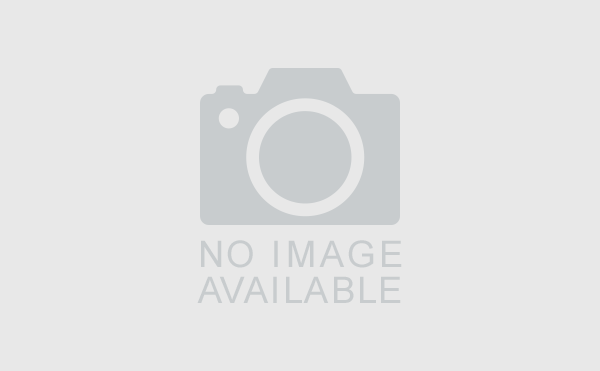日照時間の変化と睡眠の関係
皆様こんにちは。副院長の小野です。なんだか今年の夏は長くて体調を崩される方も多いかと思いますが、健康増進を考える上で睡眠はとっても大事な要素ですよね。今回のコラムでは、日照時間と睡眠との関係性についてご説明したいと思います。
私たちの睡眠は、「体内時計(概日リズム)」によって起きるタイミング、眠くなるタイミングがある程度制限されています。その最も強力な“時刻合わせ”の合図が、実は日光なのです。ちなみにこの体内時計ですが、一般的には25時間程度と言われて、もし完全に日光を遮断した環境に人間を置いた場合、活動時間が1時間ずつズレこんでいくと考えられています。そんな人間の体が持つリズムは、日光の刺激によって調整されるのです。特に朝の明るい光は体内時計を前に進め、夜の強い光は後ろへずらします。季節により日照時間が変わると、この合図の強さとタイミングが変わるため、眠気の出方や寝つきに差が生まれます。
■ なぜ冬は起きづらく、夏は寝つきにくいのか
それでは、朝の寝室をイメージしてみてください。真冬は朝もぼんやりと暗く、真夏は既にうすら明るいですよね。冬は日の出が遅く、出勤時間帯もまだ薄暗いことが多いため、体内時計を前進させる朝光の刺激が不足します。結果として「夜型化」しやすいのですが、ただ社会のリズムは変わりません。こんなギャップによって朝の眠気や日中のだるさにつながる事もあります。そしてその疲れを解消すべく、休日にお寝坊をしますと、月曜の朝が辛くなりますよね。所謂 “ソーシャル・ジェットラグ”というやつです。逆に夏は早朝から強い光を浴びやすく、体内時計が前に進みやすい一方、夜も遅い時間まで明るい環境・活動が続くと、今度は「夜の光」で体内時計が後ろへ引っ張られて寝つきが悪くなることがあります。要は「どの時間帯に、どのくらいの明るさを浴びるか」がカギです。そのため、寝室のカーテンの具合や窓の向き、間取りによっても変化しうると思われます。
また、温度や湿度も大きな影響を受けます。前提として、人間は高温高湿度の環境では眠れません。そのため、夏という時点で結構不利なのです。そして至適温湿度についてはいくつか報告があるものの、ばらつきも大きいので、敢えてシンプルにお伝えすると「布団をかぶって丁度いい、布団なしだとちょっと肌寒い」くらいの環境設定がおススメです。実は人間は睡眠中に体温や脈拍が変化し続けています。勿論恒温動物ですので、爬虫類のような極端な変化ではないですが、それでも体温が上がったり下がったりするのです。その中で寝返りをうったり、体温が下がったタイミングで布団を引き上げたり、暑くなったら足だけ出したりと、自然に体温調整するのです。この体温調整をしようとする時に、毛布でもブランケットでも良いですが、一枚羽織った状況でお休みになった方が快適ですよね。
■ 光の使い方
- 朝:起床後1~2時間以内に屋外で光を浴びる
可能なら15~30分、通勤や散歩を朝に組み込みましょう。曇天でも屋外は室内より十分明るく、体内時計を前進させる効果があります。起きづらい冬ほど「朝の屋外」を意識すると、数日で起床が楽になります。また、ガラス越しではなく直射日光であることが重要です。 - 夜:就寝前の強い光を避ける
就寝2時間前からは照明をやや落とし、スマホやPCは明るさを下げ、画面との距離を取りましょう。少なくともベッドの上でこれらのデバイスを操作することは止めておきましょう。 - 一定の生活リズム
起床・就寝時刻、食事・運動・入浴のタイミングを「毎日ほぼ同じ」にすることは、光と並ぶリズム強化策です。休日もだいたい誤差1時間以内に収めるのが目安ですね。もし土日に2時間程度お寝坊するのであれば、平日の睡眠時間が短すぎる可能性があります。睡眠は時間の確保が大事ですが、この規則性も実はとっても重要です。 - 日中の活動で“振幅”をつくる
日中の軽い有酸素運動、適度な社会活動、午前中のカフェイン(午後は控える)、夕方~夜のリラックス入浴は、眠気と覚醒のメリハリ(振幅)を作ります。健康だけが全てではありませんので、運動や嗜好品を楽しむ余裕も欲しいですよね。ご自身の生活のスタイルに取り入れられるものを考えてみましょう。 - どうしても朝が暗い場合
冬の出勤前に屋外に出られない方は、起床後に明るめの室内照明を点け、カーテンを開ける工夫をしてみましょう。ちなみに、体内時計や必要な睡眠時間は年齢や遺伝子によってある程度規定されています。 - 子ども・思春期への配慮
思春期は本来やや夜型に傾きやすい時期です。活動時間そのものが親世代とずれていることもあります。早寝早起きは悪くありませんが、実践が難しいお子さんも少なくありません。 - 夜勤・交代勤務のヒント
勤務前に明るい光で覚醒度を上げ、勤務後の帰宅時はサングラス等で朝光を避けると、不要な体内時計の前進を抑えられます。寝室を遮光カーテンや間接照明などでぐっすり眠れる環境にするのも良いですね。
■ “つまずきポイント”と対処法
就寝の"つまづきポイント"を解消するには、起床直後と就寝前の行動をルーティーン化してみましょう。アラームで起床→カーテンを全開に→室内照明オン→軽くストレッチといった形で、「難しくないことを考えずにやる」というのはとても有効です。ダイエット法やビジネス書籍等でもよく言われることですが、事前にいろいろと準備をしておき、あとはやるだけという状況を作り出すと、思いのほか継続しやすかったりします。余談ですが、私は研修医の頃に、休日になると一週間分の仕事着の洗濯を行い、曜日ごとに並べていました。また、朝食に必要な食器や食材は所定の位置に置いておき、起床と共に着替えて、食べて、そして出勤するという生活を送っていました。こうすると、朝何も考えることなく病院へ向かい、その日にやるべき仕事に集中できたのです。仕事柄、企業の要職に就かれている方やアスリートの方とお会いする機会がありますが、快適に仕事するために朝や夜のルーティーンを定めている方は少なくありません。
■ それでも整わないときは
いびきや日中の過度な眠気、寝つきに長時間かかる、早朝に目が覚めるといった症状が続く場合、睡眠時無呼吸症候群や概日リズム睡眠‐覚醒障害(睡眠相後退/前進など)が隠れていることがあります。独力で無理を続けるより、睡眠専門医へご相談ください。生活スタイルや過去のエピソードを踏まえ、必要な検査方法や治療についてご提案が出来ると思います。いわゆる睡眠薬を処方することもありますが、依存性が低いもの、生活への影響が少ないものを提案できますので、ご安心ください。
こんなことを意識しつつお過ごしになってみてください。
最後まで御覧いただきありがとうございました。
皆様がぐっすりお休みできることを祈っております。